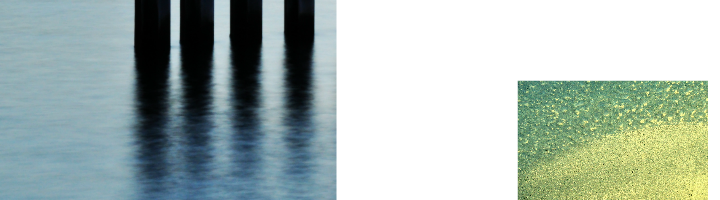アガルマⅢ 目 次
Ⅰ フッサール
1 「イデーン」に関する考察 ・・・・・・・・・・・・・・・ 5
1 還元 2 超越的―内在的 3 超越論的―自然的
4 語義的なこと―ノエシスとノエマ 5 語義的なこと
―志向性 6 感覚的ヒュレーと思考的モルフェー
7 現前化と準現前化 8 事物と射映 9 体験と反省
10 現象学の目的 11 現象学的社会学
2 「ノエシス・ノエマの構造」について ・・・・・・・・・ 52
1 中立変様 2 ノエマの核
3 「幾何学の起源」について ・・・・・・・・・・・・ 69
1 言語表現と共同性 2 歴史的アプリオリ
3 デリダの序文について
A 共同主観性としての言語について
B 共同主観性としてのエクリチュールについて
C 理念と歴史性
4 「間主観性」について ・・・・・・・・・・・・・ 109
1 「デカルト的省察」 2 明証性・志向性
3 「客観的実在」について 4 社会的客観-間主観性への道
5 固有な自我の他我統合拠点 6 間主観性の確立
7 他者経験 8 他者存在の確証性
5 「生活世界」について ・・・・・・・・・・・・・ 159
1 無記名の主観性~生活世界の明証性
2 生活世界における判断中止
6 現象学の諸問題 ・・・・・・・・・・・・・・・ 180
1 超越論的主観と生活世界 2 生活世界・発生的現象学
3 共同主観性 4 癒合的社会性 5 志向性
7 「存在妥当性」の問題――竹田青嗣「意味とエロス」・・214
1 存在妥当 2 欲望 3 生きる意味
4 現代哲学 5 デリダ批判
Ⅱ デリダ
1 デリダについて ・・・・・・・・・・・・・・・・ 257
1 声 2 いくつかの概念
脱構築 痕跡 代補 差延
3 「論理学研究」―表現と意味 4エクリチュールについて
2 暴力について ・・・・・・・・・・・・・・・・ 280
1 悲しき熱帯 2 第三項排除―アウスシャルテン
3 デリダの暴力批判-レヴィナスへ
A 存在的暴力 B 根源的論戦 C 超越的暴力
3 パルマコン ~ 治療薬/毒薬 ・・・・・・・・・ 325
1 エクリチュール 2 パルマケウス=ソクラテス
Ⅲ レヴィナス
1 「全体性と無限」 ・・・・・・・・・・・・・・・ 343
1 全体性と終末論 2 <同>と<他>
3 歴史の死 4 ハイデガー批判 5 渇望―形而上学
6 エロスの現象学
a 女性性 b愛撫 c エロス的な裸形 d官能の閉域
7 裁き 8 il y a・・・<ある>
9「脱存主義」<extasime >と「イポスターズ」実詞化<hypotase >
10 他者 11 逃走 〔付〕レヴィナス略歴
2 「レヴィナス後期の思想について」 ~村上靖彦「レヴィナス」から
・・・・・・・・・・・ 428
1 呼びかける他者 2 精神疾患と
通常人のバランス感覚
3 歴史哲学 A 起源について B 破局について
Ⅳ その他
1 カントの認識論 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 445
1 純粋直観 2 論理学 3 カテゴリー
4「現象としての物」と「物そのもの」
5 構想力と図式 6 理性と悟性 7 アンチノミー
2 ヘーゲル「精神現象学」 ・・・・・・・・・・・・ 483
1 意識と対象 2 自己意識と欲望
3 主人と奴隷―支配と従属
<参考文献> <あとがき> ・・・・・ 504
<あとがき>
* 今回の「アガルマ」の編集には時間がかかった。扱っているものがフッサール、デリダ、レヴィナスと、どれも現代思想を論じるにあたって逸することのできない人物達でありながらフッサールは無味乾燥(「危機」と「デカルト的省察」を除いては)、デリダとレヴィナスにおいては晦渋,難解であって、私のキャパシティを超えることが多々あった。
* しかし「認識論」と「存在論」にあっては竹田青嗣が「エロスと意味」において明快に「存在妥当」の概念で読み解いてくれているのでプラトンの「イデア」カントの「物そのもの」以来の存在を妥当性の概念で考えることができる。(勿論フッサールの功績なのだが・・・)
また「間主観性」(共同主観性)に関してはフッサールの「デカルト的省察」第五章及びメルロ・ポンティの「幼児の対人関係」(癒合的社会性)によってほぼ解くことができていると思う。その件を更に延長していくと、共同主観性を担っているのが「言語」であることがわかってくる。ここからデリダのエクリチュール論に繋がっていく。まさしく言語こそが文化的な意味での共同主観性なのだ。
更にデリダの問題提起は「形而上学と暴力」論文においてレヴィナス批判に向かう。
* レヴィナスの「全体性と無限」は彼の初期の問題意識の総決算であるが、そこに貫かれている問題意識は自らもドイツの捕虜となり、家族の殆どをショアー(Shoah=ホロコースト)で虐殺された彼なりの全体性への抗議である。
全体性に同一化して虐殺に加担していく群集、知識人、政治家達に対して同一化しない<他者>を殆ど神の極限にまで引っぱっていった彼の論考は、極端にすぎてデリダの穏当な、また当然の批判を生んだが、暴力の止揚を自由との対比の中で正義として描いて見せた論考であった。
* レヴィナスはデリダの批判を受けてから、それ以前の転換の準備を加速させ、「存在の彼方へ」を出版する。この件については村上靖彦の「レヴィナス」を借りて概説した。共同体の<起源>への回帰、あるいは<起源>さえもないものから出発しうる構想力をショアーや大災害の受難に耐え抜き対応しうる感性の産出に賭けるところに、未来へのアイデアがあるように思う。
* カント、ヘーゲルについては「物そのもの」論と「主人と奴隷」論の確認である。
* なお必要な個所に原文を添えた。
2013.10.15
徳永省三