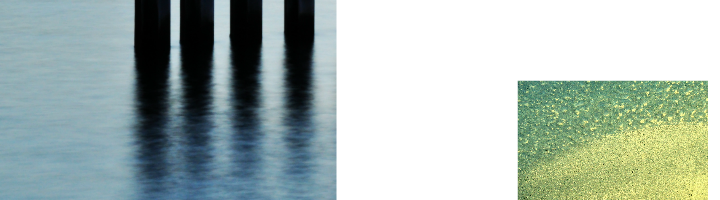「アガルマⅡ」
「アガルマⅡ」 目次と後記
<アガルマⅡ 目 次>
1 哲学史 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
哲学、形而上学の意味
1 デカルト 2 カント 3 ヘーゲル
2 ハイデッガー論考 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
A 「存在と時間」ノート
存在と時間(1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
1 存在、現存在、実存
2 存在論の歴史的解体
3 現象学の存在論的意味
4 デカルト哲学の原理
5 ハイデッガーのデカルト批判
6 世界=内=存在
7 内=存在・・・気分
8 了解と解意
9 話、世間話、好奇心、曖昧さ――頽落
10 不安と関心
11 カントの外界問題
12 真理はどこに
存在と時間(2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86
1 死に臨む存在
2 先駆性
3 覚悟性、状況
4 良心と負い目
5 先駆的覚悟性
6 既往・将来・現在――時の脱自態と時熟
7 現持・瞬間・反復
8 時熟・地平的図式
9 科学的了解
10 運命と反復
11 歴史的時間
12 世界時間と通俗的時間
13 ヘーゲルの時間論
(1)空間と時間
(2)時間と実在的なもの
(3)持続するもの
(4)ときは今、今は永遠
(5)カントの時間論
(6)ヘーゲルの時間論批判
***終わりに
B ヘルダーリンの讃歌――ゲルマーニエン、ライン ・・・・・・ 181
1 ゲルマーニエンGermanien
2 詩作について
3 ヘラクレイトス a)ヘルダーリン
b)ヘラクレイトス
c)ヘーゲル
4 ドイツ的大学の自己主張
a)演説 b)日本での反応(田辺、三木)
c)K.レーヴィット d)菅谷規矩雄
5 「ライン」への思索
C 「哲学への寄与論稿」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 271
1 最後の神 letzte Gott
2 「世界観」対「哲学」
3 性起 Ereignis
4 元初・・・「第一の元初」と「別の元初」
3 和辻哲郎 論考 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 293
1「風土」
2 美的生活について (S.キルケゴール)
3 芸術について(F.ニーチェ)
1 ディオニソスと救済
2 芸術的真と宗教的真
3 美学 4 カント批判
5 絶対知と喜劇
4 日本文化・日本思想について
5 古寺巡礼
6 古代文化
< 後 記 > ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 426
< 後 記 >
***
ハイデッガーの「存在と時間」は、第一次世界大戦の敗戦国であったドイツにあって、思想界では新カント学派や意識の現象学だけでは物足りず精神的支柱を求めていた人びとに衝撃をもって迎えられ、あっという間に世界に知れわたった。
この書は実存主義の基となり、サルトルたちにも大きな影響を与えた。もっともハイデッガー本人はこの書を「実存」の強調としてではなく「存在」論として書いたことを後に明らかにして世間の思惑を否定した。事実この書の後に継続されたハイデッガーの思索は未完の「時間と存在」論へと向かっていき、やがてその全貌は「哲学への寄与論稿」へと結実する。しかしこの書は著者の遺言により死後しか発刊を許されず、ドイツで発刊されたのが1989年、日本で訳書が出たのが2005年という最近の出来事なのだ。そのため後期のハイデッガーへの評価、論評は未だこれからという感じである。その中でも小野真の「ハイデッガー研究」は1999年に書かれたものだが、ハイデッガーの全著作を通覧し、熟考されたもので、今後ハイデッガーを研究される方にはお薦めしたい一冊だ。
未完の書、「存在と時間」については、梅原猛などが大学時代3年間こればかり読んでいたことを告白しており、ある意味で《青春の書》と言ってもいいのではないかと思わせられる部分も多い。なかでもやはり「先駆的覚悟性」を扱った第一部第二篇は感銘が深く、「存在と時間」全編を読む余裕がなくても、この部分だけは読んで損はしないと思う。
ハイデッガーのナチスとの関係についてはいろいろと本が出ているようだが、私のこの論文ではK.レーヴィット、田辺元、三木清、菅谷規矩雄の直接の批判及び間接的に(和辻批判として)戸坂潤のものを挙げておいたので参照されたい。
後期のハイデッガーに関しては、<第一の元初>古代ギリシアの自然哲学~近代哲学~ニーチェを経て終焉した形而上学が、そこから<別の元初>へ立ち帰って新しい形而上学の歴史が始まることを雄渾な予言的筆致で描いた「哲学への寄与論稿」の思索の強靭さに脱帽させられる。「存在と時間」が20世紀哲学の金字塔であるとするなら、「哲学への寄与論稿」は21世紀哲学への予言的な書であることは間違いないであろう。
***
後半の「和辻哲郎」論は、思想におけるナショナリズムの問題を解くのにこの著者ほどまともなものはないように思えたので、その検討の前半部分を掲載した。
戦後、象徴天皇を支持し、保守派として非転向を貫いた和辻だったが、ブリリアントな文体に一貫した主張を貫いて好感をもてる。師と仰ぎ、しかしこの端麗さに物足りなさを感じていた梅原の戦後の軌跡も面白いが、和辻の才気溢れる文体はなかなかのものだ。
***
全体に「アガルマⅡ」は引用文の注解の如き文章が延々と続き恐縮してしまうが、いわば「哲学」の門前に誘うテキスト本としては、これはこれでいいかな、とも思う。自分なりのオリジナルな論文は書きたいのだが、進めば進むほど世界の大きさに戸惑いを感じてなかなかオリジナルなものを書くことが難しい。
***
(表記上のことについて)
ハイデッガーの「存在と時間」について、細谷訳では原書の斜体の単語が傍点を振る形になっている。この傍点については一切振らなかった。
「ゲルマーニエン」の訳には木下訳と川村訳の二つを掲げたが、一読してもらえれば両者相当の隔たりがあることが分かってもらえるだろう(文語、口語という差異以外に)。ただしハイデッガーの本文読解のためには本文を訳した木下訳でないと分からない部分があって、「ゲルマーニエン」読解に関しては両者を比較してもらうと同時に原文に当たってもらうのがいいと思う。散文の場合でも訳者によって翻訳のニュアンスが相当異なっており、詩に至ってはもはや翻訳者の創作だとしか思えないものもあり、詩に関しては原文しか本作としてはいけないように思う。散文に関しては拙い語学力で読むよりは名家の翻訳で読むに越したことはないが・・・
2012.11.10 徳永省三 記