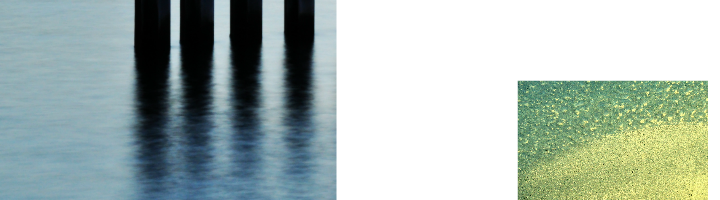「アガルマⅠ」
1 「アガルマⅠ」
目次と後記
<ア ガ ル マ Ⅰ 目 次>
1 「ポスト」についてーーポストモダンの漂着 ・・・・・・ 3
1 ポストモダン 2 ポストモダンの意味 3 パラロジー
2 ラカン的なもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
1 鏡像段階 2 シェーマL 3 象徴段階
4 去勢――欲望の禁断 5『対象a』と欲望 6 他者の欲望
7 主と奴隷の弁証法――パラノイヤ的情熱
8「もの」の殺害――象徴化への道 9シニフィアン
10 語りえぬもの、出会ええぬもの
3 西田幾多郎--アジア的思弁 ・・・・・・・・・・・・ 57
「善の研究」 1純粋経験 2思惟と真実在 3自然、精神,神
4 善の研究 5 宗教--神
「自覚について」
「絶対無について」 1有、無、絶対無
2ノエシス・ノエマにおける絶対無
3歴史的限定 4内的生命
5絶対無の立場への批判
(1)哲学と宗教
(2)絶対無は否定性を説明できない
(3)フッサール、ハイデッガーの限界
(4)歴史意識について
(5)無の論理は論理であるか?
「場所の論理」 1 場所 2 欲望
「歴史意識について」
4 田辺 元ーー弁証法的実存協同 ・・・・・・・・・・・ 103
「絶対弁証法について」1 絶対弁証法そして「表現」
2 普遍の外化と表現・身体
3 愛による運命との和解
「種の論理」 1「絶対媒介」と「類・種・個」の思考
2 種の分析、「種」と「類」の関係
3 類の展開――国家
4 種の構造
5 種の論理がめざすもの
「偶然性について」 1偶然性と必然性 2無と偶然性
「マラルメ覚書」について 1詩と思想 2時の構造
3愛における実存協同性
4「イジチュール」と「双賽一擲」 5 運命と偶然
5 三木 清 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 162
「危機意識の哲学的解明」について
< 後 記 >
* 近代が準備した「大きな物語」が半壊して私たちは生きる支えを失っているかのように見える。暗黙の標識であったものが崩れ去ってみると種々(くさぐさ)の「小さな物語」が積み木のように積み重ねられていって、そのうち何の正当性の保障もないないまま崩されていってしまうのを目の当たりに見たりする。
何か輝かしいものが向こうにあるという期待によって開くのを待っているカフカの「掟の門」の田舎者のように、そうやって虚しく老いて、こと切れてしまう人生がある。時代の正当性といったものが守ってくれる、などという保証などは何処にもないのだ。
* 福原泰平の「ラカン」は久しぶりに面白いラカンの解説書だった。これほど人生が見えている人なら何も町の精神科医なんてやっている必要性もないのでは、と思うくらい喪失の映し出す影絵の描写が美事だ。なるほど盲いて初めて真実を知るオイディプスのように目があいていても「見れども見えず」の人生を私たちは歩んでいる。
門の向こうには「アガルマ」(ラカンは対象aのことをこう呼んでいた。)があるように思ってしまう。「アガルマ」とはギリシャ語で輝かしく魅惑的なもののことだ。(アルキビアデスがソクラテスに見たような)アガルマは生きる原動力だが、それが朽ち果てたものであったとしたら、人間はどんなにか絶望に陥ってしてしまうことだろう。
* 半年前に中沢新一の「フィロソフィア・ヤポニカ」を読んで感心した。西田と田辺の両方についての評論だが、どちらかといえば田辺への肩入れが著しい。もう10年以上も前に(1999年~)書かれたものだがその斬新さは色褪せていない。20世紀に至って絶対無を中心に展開された西田の思索は哲学の伝統のない日本にあって、確かにアジア的なものを基盤に据えたオリジナルな哲学であったと思う。それに拮抗した田辺も弁証法を駆使しながら西田という「他者」を鏡に独自の実存協同の哲学を築いていった。2000年もの空白のある、哲学することの困難な風土にあって、そのギャップを性急に埋め前へ飛び出そうとする爽快なエネルギーを感じた。
戦争を挟んで時局の動乱の中で泥まみれになった思想は、果たして現代に生きていくことができるのであろうか。「大きな物語」を喪った今となっては哲学のボルトを締めなおして「生き方」の本体を駆動しなおしていかねばならない。昔、ギリシャの哲学の雇われ教師のことをメテクと言ったそうだが(パリではアラブ人の蔑称らしい)何の係累も学問所ももたないメテクとして日本の骨を拾いなおしていかねばならない。
2012.3.14 徳 永 省 三