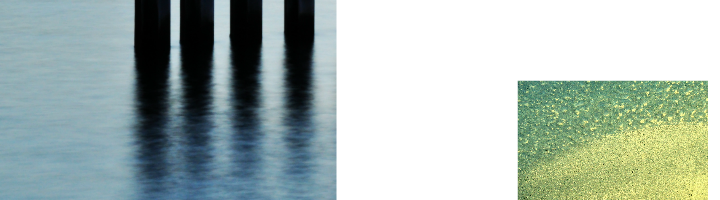新 刊 「Ambientな哲学」2014.8.20
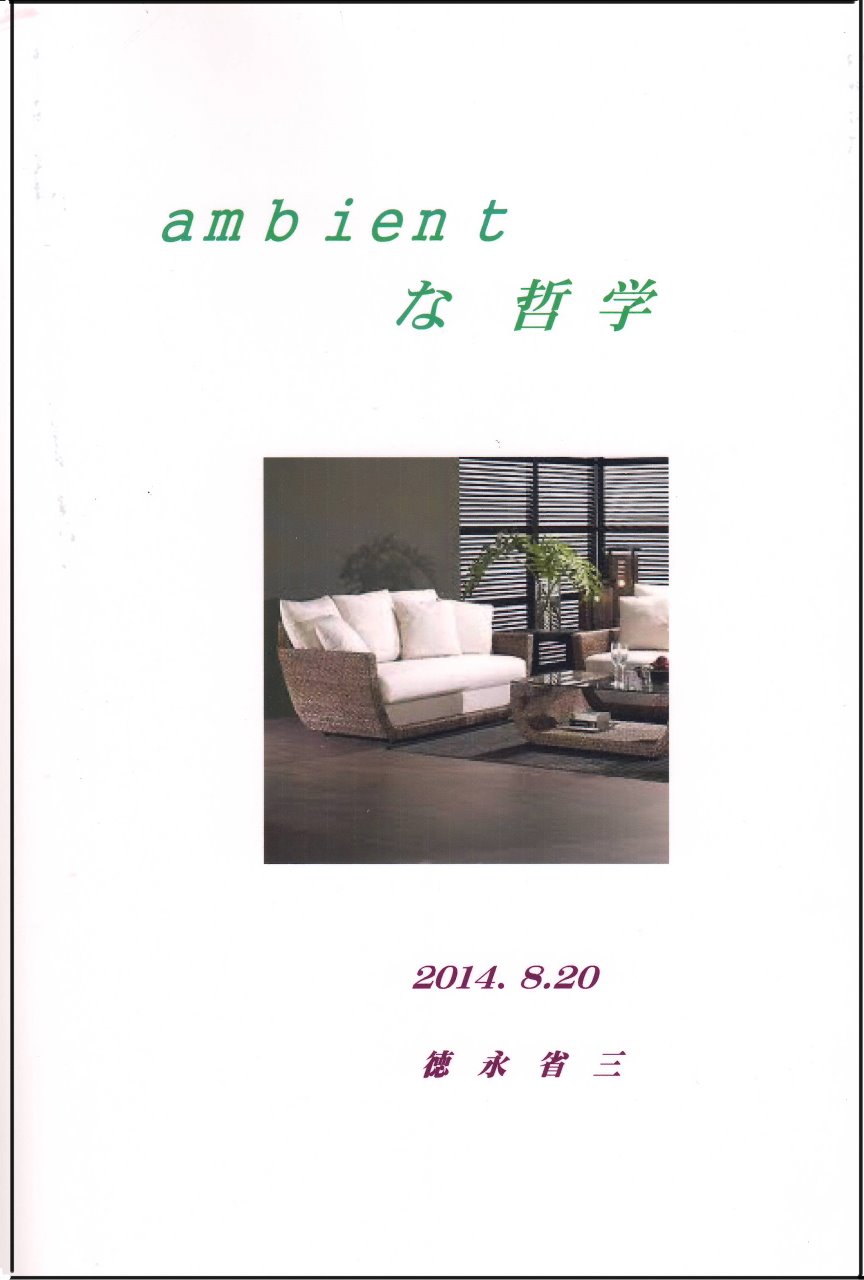
Ambientな哲学 目 次
哲 学
1 系譜学について
2 永遠回帰となでしこ
3 永遠の命はあるか(1)――輪廻転生と終末論
4 永遠の命はあるか(2)
5 おひとりさま考――一期一会
6 私と汝――西田哲学と臨床精神医学
7 新しい冷戦の始まり――力への意志
8 死に関しての科学的ニヒリズム批判――3つの死生観
9 哲学するとは何か――ambientな「家具の哲学」
精神臨床
1 死にたくなったら全力で逃げろ
2 トリエステ(1)――マットと薔薇
3 連れ去り事件の真相(深層)
4 無敵の人――「黒子のバスケ」脅迫事件
5 「途絶」について――記述と沈黙(顔)
6 残虐な少年事件――佐世保
文 学
1 トリエステ(2)――サバとひとりの女
2 益子直美――上を向いて歩く?
3 ピダム――愛の疑惑(「善徳女王」)
4 忍びよる破滅と傍観者――鴎外の小説の主人公たち
時 事
1 西村主審の采配――ブラジル対クロアチア
2 フェミニズムへのテロ――都議会セクハラやじ
3 裁判員裁判の陥穽――求刑超え
4 有敵の人――ある科学研究者の死
<あとがき>
今年の5月頃から書いてきたブログをまとめて1冊にすることにした。
今回はニーチェを参照枠にして時事問題を論じることが多かった。
結論的には"ambientな哲学"に行き着いた。これはカジュアルというのとはまた違う意味で"くつろげる"といった意味を持っている。ニーチェが"鉄槌を以ってする哲学"と言ったのに対してそんな大仰なことはやめて、哲学を日常生活のさりげない所に見出して違った視角から物事を考えてみるといった風な意味合いである。丁度サティが自分の音楽を"家具の音楽"と呼んだように身近な問題に対しての新しい視角は異なったくつろぎを与えてくれることだろう。
解決されていない"哲学の大問題"はあることはあるが、哲学することが茶の湯を営むように日常茶飯となるような営みとなるなら、それは生活に一陣の風を呼び込むに違いない。そういう出発点に今、立ったような気がする。
2014.8.20
徳永省三