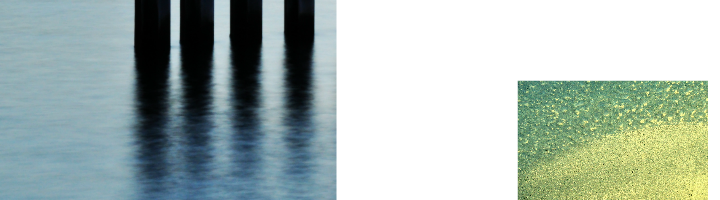コラム
(1)映画「Lie with me」(邦訳「寂しい時は抱きしめて」)
「Lie with me」の日本語訳が「寂しい時は抱きしめて」とは驚いたが、まあそういう意味だろう。
カナダの映画。2005年公開。監督クレメント・ヴァーゴ、主演ライラ=ローレン・リー・スミス、デビッド=エリック・バルフォー。
偶然You Tube で見つけて原語のまま男女の成り行きを(SEXも含めた愛情シーンを)
なんとなくわかったつもりで見ていた。ライラのアダルトビデオを見ながらのオナニー・シーンなども最初と最後に挿入されている・・・といってこれは決してアダルトビデオであるわけではない。ふと知り合った男女がsexに迷い込み、互への違和感をぶつけ合い離れ離れになりそうで、それでいて最後には結びついていく話だ。一様SEX シーンがふんだんなのでR18指定映画で、日本語訳付の日本公開(2007年?)ではぼかしがひっきりなしに出てきてうんざりしたという話だ。その点原画のままの作品では無修正のままである。日本でも無修正の時代が来るとシリアスものの男女俳優も隠すところなく苦労する時代が来るのだろうか。
その無修正部分で一番面白いシーンは知り合ってまもなく二人とも素っ裸でダンスを踊るシーンだ。その前段にペニスをバスタオルで隠して女を牛に見立てて誘導するシーンがあって笑わせられる。その続きに紳士淑女の全裸ダンスシーンがやって来る。立っているとやはり男のもののほうが目立つ。男は得なのか損なのか。
あらすじなどは概略しかわからない。クラブで踊り男を漁りに行っていたライラの前に男前のデビッドが現れる。ライラの気まぐれに選んだ男とのライブハウスの裏手での交情のシーンにに偶然女友達とデビッドが車でいちゃついている。ライラもデビッドもこのことに気付き、両者のフェラチオ場面で互いを見つめあいながら達するという奇妙な経験をする。いずれにせよ二人は惹かれあい、公園で一緒になったのをきっかけにデビッドの家で結ばれる。
二人の家庭にはそれぞれ不幸があってデビッドの父親は半身麻痺、息子の介護が必須だ。ライラの家庭は夫婦不和で離婚寸前である。二人の接近につれてこの不幸も忍び寄ってきてやがてデビッドの父親はなくなり、ライラの母親は家を出て行く。二人を襲う不幸は気晴らしのSEX では片がつかなくなり、ちょっとした異性関係のもつれで仲たがいしてしまい、二人は性の荒野に投げ出されてしまう。もちろんこの映画はハッピーエンドで終るのであって、ライラの友達の結婚式で顔を合わした二人は互いに離れがたいものと確認しあう。
この映画の面白さはsexシーンがアダルトビデオのような性技巧の見せびらかしや、動物的グロテスクな器官の強調、遊戯的な場面ばかりが繰り返されるのでではなく二人の感情の自然な移り行きに即した触感と接近がさりげなく自然に描かれていることだろう。
そういう意味でも愛というものが抽象的に前景に立っているのではなく、心理の機微とからだの触れ合いが自然な性的接触の軌跡を描いていくところが見事に描かれていて秀逸である。
2013.1.29
(2) ピナバウッシュPina Bauschについて
ピナバウッシュは2009年68歳で死去したタンツシアターを主催した現代舞踊の巨匠であった。前年琵琶湖ホールで「フルムーン」を踊ったのが最後の公演であった。フェリーニの「そして船は行く」や坂本龍一のオペラ「LIFE」などにも出演しているが、勿論タンツシアターDas Tanz Theaterでの作品や舞踏ビデオ、公演が本流であって次のような作品を残している。
「春の祭典」(1975年)
「七つの大罪」(1976年)
「カフェ・ミュラー」(1978年)
「カーネーション」(1982年)
「ヴィクトール」(1986年)
「パレルモ、パレルモ」(1989年)
2007年には京都賞を受賞している。
大作でも50分足らずで、クリップという形での小品も多い。私は「春の祭典」や「カフェ・ミュラー」以外にこの小品集をビデオで見た。
(ピナの軌跡についてはヴェンダースの映画「ピナバウッシュ踊り続けるいのち」、またビデオ「Das Tanztheater der Pina Bausch」「Un Jour Pina m'a demandé1983」などがある。)
|
|
|
|
1 Love |
10 senza peso |
|
2 Lean on me |
11 l'apparenza inganna |
|
3 fiducia |
12 Ragazzo con vesito a fiori |
|
4 La Prima Vez |
13 Life |
|
5 Joy |
14 seasons march |
|
6 Fun |
15 traiar original |
|
7 Dance Hall |
16 by Wim.wmv |
|
8 Love Dance |
17 The here and After |
|
9 Reconciliation |
18 shooting on location |
“ Love ”という作品を見てもわかるがピノの作品の主要なモチーフには〈愛>というものが置かれていることは間違いないであろう。それも愛と離反、憎しみと和解、執着と死といったような相反する矛盾が解きがたくまとわりつくような感じで表現しつくされている。勿論全てが充足的に描かれるのではなく、禅画の隅の空白部分のように得体の知れない謎の空白を残して消えていくのである。
愛についてはヴァレリーの有名な対話編「魂と舞踏」(清水徹 訳)の中のパイドロスの言葉
愛の魂とは愛しあうふたりのあいだの打かちがたい差異であり、他方で愛の精妙な実質は愛しあうふたりの欲望の同一性です。だから、舞踏は四肢の描きだす線の精妙さ、跳躍の神々しさ、爪先で静止するときの繊細さによって、肉体も顔ももたず、天賦の才と日々を、そしてさまざまな運命をもち、しかもひとつの生とひとつの死とをもつ、あの普遍的な被造物を産みださねばなりません。その普遍的な被造物とはまさに生に他ならず死に他なりません、というのも欲望はひとたび生まれたあとは、睡眠もいかなる休息も知らないのですから。(パイドロス)
愛は「打かちがたい差異」であり、他方で「愛しあうふたりの欲望の同一性」であると。
以下、話は変わって、舞踏については、対話編「魂と舞踏」の中に出てくる舞踏の女王アティクテについて登場人物の3人の評を挙げてみよう。
ここでは床は、リズムの乱れや不安定の原因をなすものすべてが念入りに除かれ、いわば絶対的なものとなっているので、この堂々とした行進は、みずから自身だけを目的とし、一切の変わりやすい不純物も消え去って、ひとつの普遍的なモデルとなるのです。見たまえ、何という美しさ、何という充実した魂の平静さが、彼女の高貴な脚のひと跨ぎ、ひと跨ぎの距離の長さから生まれてくることか。彼女の歩みのこの豊かさは歩数と一致し、その歩数は音楽から直接に発している。だが、歩数と歩幅は、他方では、背丈と密かに調和している・・・(エリュクシマコス)
呼吸と心臓のこころよい中断!・・・ 重みが彼女の足下へと落ちてゆく。音もたてずに崩れ落ちるあの大きな薄紗がそれを理解させる。彼女の身体は動きのなかでしか見て
はならない。(ソクラテス)
ちょうど、屋根の縁ぎりぎりのところまで来た小鳥が、美しい大理石と訣別して、飛翔のなかへと落ちてゆくような瞬間……(パイドロス)
彼女はまずはじめに、精気あふれるその足どりで、大地から、あらゆる疲労、あらゆる愚劣を消し去るかのようだ…… それから、見たまえ彼女は、もろもろの事物のすこし上のほうに、みずからひとつの住処をつくりだす、それはまるで白い両の腕のあいだに巣をしつらえているかのようだ…… だがいまの彼女は、さまざまな感覚よりなる定義しがたい絨毯を、その両足で織っていると思えないだろうか?・・・ 足を交叉し、また交叉を開いて、持続でもって地面を織りあげてゆく。おお、攻めたててはひらりと避け、結んでは解き、追いかけあっては、ぱっと跳びあがる、その聡明な足のつくりなす魅惑的な作品、きわめて貴重な作業!……何と巧みなことか、何と活き活きとしていることか、失われた時の悦楽をつくりだすあれらの純粋な職人たちは(パイドロス)
彼女は薔薇を、絡み合う曲線を、運動の星々を、そして魔法の囲いを描きます…… 円環が閉じたかと思うと円環の外へと跳びだします……跳びだしては、幻影のあとを追って駆けてゆきます!・・・ 花を一輪摘みとったかと思えば、それはたちまち微笑に他ならない!・・・ おお!・・・ 何と彼女は、汲みつくしえない軽やかさで、みずからの非存在を明言していることか!・・・楽音のただなかに迷いこみ、一筋の糸にすがって身を取り直す…… 横笛が救いの手をさし伸べて彼女を救ったのです!・・・ おお、旋律!(パイドロス)
変身に続く変身という純粋持続によって何ものかを描こうとするアティクテ。しかし人生の毒液をソクラテスは「倦怠!」とつぶやく。エリュクシマコスはそれに対して絶望的に答える。
おお、ソクラテス、宇宙は、みずから在るがままのものでしかないことを、ただの一瞬たりと許容することができません。奇怪な考え方です、〈全体〉であるところのものが、みずからに充足しえないとは!・・・それゆえに宇宙は、在るがままのものであることへの怖れから、みずからのために無数の仮面をつくりあげて、みずからの素顔の上に描いてきました。なぜ死すべき人間が存在するのかという理由も、それ以外にはありません。死すべき人間は何のためにあるのか?――人間の仕事は知ることです。知ること?それならば、知るとは何か?--それは、まぎれようもなく、自分が在るがままのものではなくなる、ということです。-―したがって、人間どもは錯乱し、思考し、自然のなかに際限のない誤謬の原理と、あれら無数の驚異を導入するのです!・・・
誤解、外見、精神の屈折光学の戯れが、世界というみじめな塊を掘りさげ、活気づける…… 観念は、在るもののなかに、在らざるもののパン種を仕込む…… でも、結局のところ、真理がときおりくっきりと現れては、幻影と誤謬の調和のとれた体系のなかで調子はずれな音を響かせる…… するとたちまち、一切があやうく滅びてしまいかねず、そしてソクラテスが御みずから、わたしに治療法を訊ねにやって来られる、明察と倦怠のこの絶望的な症状のために!・・・ (エリュクシマコス)
それに対してのアティクテを借りてのソクラテスの見解。
――彼女は、火にも比べられるような基本要素のなかで、――音楽と動きとの繊細きわ
まる本質のなかで、汲みつくしえぬエネルギーを呼吸し、まったく楽々と生きているかのようであり、他方で彼女は、彼女の全存在をあげて、極限の至福の純粋にして直接的な暴力に参与している、と。――もしわたしたちが、みずからの重苦しく深刻なありようを、あの煌めく火蜥蜴に比較するとき、きみたちにはこう思われはしないだろうか?必要に応じてつぎつぎと産みだされてゆくわたしたちのふだんの行為、わたしたちの偶発的な仕草や動作は、粗悪な原材料、持続の不純な実質のようなものであり、――他方であの生命の昂揚と振動、あの緊張の支配、ひとがみずから獲得しうるかぎりのこの上ない敏捷さにおける、あの恍惚状態は、焔の功徳と力をもっている、と。そしてまた恥辱、厄介事、愚直、また生存の単調な糧は、その焔のうちに焼きつくされて、ひとりの死すベき身である女のうちにある神々しいものを、わたしたちの眼に輝かせてくれる、と思われはしないだろうか?(ソクラテス)
だが、焔とは何だろう、おお、わが友よ、瞬間それ自体でないとしたら?-一瞬そのもののなかにある、狂おしいもの、陽気なもの、ただならぬもの!・・・ 焔とは大地と天空とのあいだにあるこの瞬間の行為だ。おお、わが友よ、重たい状態から精妙な状態へと移行するものはすべて、火と光との瞬間を通過してゆく・・・(中略)--大いなる〈舞踏〉とは、おお、わが友よ、虚偽の精神と、虚偽である音楽とにすっかりとり憑かれ、無なる現実の否定に酔いしれた、わたしたちの身体全体からの解放ではないだろうか?――見たまえ、焔が焔に置きかわるように跳躍するあの身体を、見たまえ、何とその身体が真実なるものを踏みつけ、踏みにじっているかを!いかにその身体が、みずから身を置く場所を、怒り狂いまた喜ぱしげに、破壊しているかを、そしてまたいかにその身体が、みずからのかずかずの返歌の過剰に陶酔しているかを!(ソクラテス)
そこにいた女は無数の姿態によって貪り喰われている…… 活力の火花が飛び散るさなかに包まれたあの身体は、わたしに、ある無限の思考を提示してくる。すなわち、わたしたちは自分の魂に、もともと柄ではないたくさんの事柄を求めて、わたしたちを啓発し、予言し、未来を推測してくれと要請して、〈神〉を発見してほしいとまで懇願するのだが、-それと同じように、あそこにある身体は、自分自身の完全なる所有へ、そして栄光の超自然的な頂点へと到達することを望んでいるのだ…… だが、魂にとっては身体にとってと同じで、〈神〉と、魂自身に要求される英知と深さとは、瞬間でしかなく、瞬間でしかありえない、閃光、よそよそしい時間の断片、みずからの形態の外への絶望的な跳躍でしかなく、そうでしかありえないのだ……(ソクラテス)
絶望的な跳躍としての<瞬間>。しかしこの時アティクテは言う。
避難所、避難所、おお、あたしの避難所、おお、〈渦巻〉!――あたしはおまえのなかにいた、おお、動きよ、あたしはありとあらゆるものの外にいた……
2013.2.1
(3) フェリーニ「81/2」について
最近2本のビデオを見た。一つはヴェム・メンダースの「ベルリン天使の詩」 (1987)いまひとつがこれ、フェリーニの「81/2」(1962)だ。いずれも白黒(いや、「ベルリン天使の詩」は後半でカラーになる。制作年代も25年の開きがある。もっともフェリーニは次作(「魂のジュリエッタ」「サテリコン」など)では、カラーに転じたようだが・・・
(1987)いまひとつがこれ、フェリーニの「81/2」(1962)だ。いずれも白黒(いや、「ベルリン天使の詩」は後半でカラーになる。制作年代も25年の開きがある。もっともフェリーニは次作(「魂のジュリエッタ」「サテリコン」など)では、カラーに転じたようだが・・・
8作を作り終えた後フェリーニはスランプに陥った。この作品はそのスランプ状態を自分の少年時代の回想も絡ませながら、映画監督グイドの狂気と妄想、爆発とノスタルジヤのイメージを使って描いていく。妻ルイザとの不仲、新しい恋人カルラとのアヴァンチュール、永遠の恋人クラウディアとの食い違い、どうやらグイド・ハーレムは崩壊寸前である。新作は核戦争真近の世界にあって、ロケット打ち上げの巨大セットが舞台なのだが、この新作はグイドの逡巡によって一向に前に進まない。グイドの同僚、女優達、父母、妻、愛人、カトリック司教などが入り乱れながら話が進展し、最後は「生は祭りだ、共に行きよう!」という合図の後、ヤブレカブレのハッピーエンドとなる。
この作中で出色なのはやはり、少年時代の回想シーンだ。一つは葡萄風呂に入るのを嫌がって逃げ回るグイドが捕まって風呂に入れられ、その後就寝につく場面で"ASA NISI MASA" という呪文の謎が解き明かされる。女中が寝静まった子供部屋から出て行くとさっそく狸寝入りの姉が起き出して今夜の重要性を説き始める、「今夜は壁の肖像画の目が動く日なの。その動く方向に宝があって、それを手に入れる方法が 呪文"ASA NISI MASA"を唱えること!」宝は手に入ったのだろうか?
いま一つは、乞食の娼婦サラギーナが浜辺でルンバを踊るシーン。放課後小学生らしき男の子の一団が冬の浜辺の石造りの小屋にやってきて、からかい半分にサラギーナを誘う。「サラギーナ、ルンバを踊れ」「まず、金」金を手にし、突然かかるルンバの曲ににサラギーナは目をギラつかせながら、喜色満面その巨体を揺すり始める。子供たちは大喜びで跳びあがったり、自分の頬を左右にひっぱたいたりしている。サラギーナの踊りは佳境に入る。悦に入ったくびれた彼女の腰の下の巨大な尻がぷりぷりとルンバに合わせて微妙にツイストされる、とうとう帽子をかぶり、黒いロングコートを羽織ったグイドは踊りの相手として押し出され、捕まえられ、二人楽しげに踊っている最中に担当の教師がやってきて連れ戻され、ひどいお仕置きを食らうのである。(このサラギーナの踊りのシーンは1963年のモスクワ国際映画祭の審査会場で熱狂的な拍手喝采を受けたシーンだったそうだ。)
全編モノクロだがホワイトの優しさがことさら目を惹くシーンが多かった。
2013.3.1
(4) 「ベルリン天使の詩」について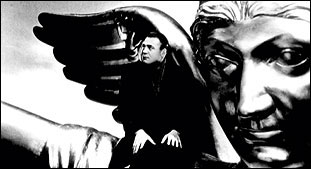
ティアガルテンの勝利の女神像にのっかている天使ダミエルの写真でおなじみとなった、
この映画は、(男の)天使が地上の女に恋をして新しい地上の生活を始めるという話なのだが、作成年が壁崩壊の寸前(1987年)だったのでいたるところで落書きされた壁の映像が映されている。
映画の中にはピーター・フォークがコロンボさながらに役者役として登場し、子どもにしか見えない天使の声を察知する。天使カシエルはダミエルの友人でダミエルの相談役となる。ダミエルの恋するサーカスの空中ブランコの女性マリオンは、天使の羽をつけて飛ぶ。この女性に恋する必然性はどこにもない。しかしダミエルはライブハウスでついに愛を告白する。このあたりからカラー映画になる・・・
ところで、一番この映画で触れたいことは天使と人間の女がうまくやっていけるのか(まるで、人魚と王子がうまくやっていけるのかみたいな・・・)といったことではない。この映画でしょっちゅう出てくるフレーズ
“Als das Kind Kind war"
子どもが子どもだったころ
******
についてである。
******の部分には大人が失った子どものナイーブで頑固な面が付け加えられる。冒頭で語られるのは次のようなものだ。
Als das Kind Kind war,
ging es mit hängenden Armen,
wollte der Bach sei ein Fluß,
der Fluß sei ein Strom,
und diese Pfütze das Meer.
Als das Kind Kind war,
wußte es nicht, daß es Kind war,
alles war ihm beseelt,
und alle Seelen waren eins.
子どもが子どもだったころ
腕をブラブラさせ
小川は川になれ川は河になれ
水たまりは海になれと思った
子どもが子どもだったころ
自分が子どもだとは知らず
すべてに魂があり
魂はひとつだと思った
以下原文がわからないが
(子どもが子どもだったころ/ なにも考えず/ 癖もなにもなく/ あぐらをかいたり
とびはねたり/ 大きな頭に/ 大きなつむじ/ カメラを向けても/ 知らぬ顔 )
こどもの視線は無邪気で残酷だ。しかもリアルで空想的。映画はAls das Kind Kind war,
を折々挿入しながら子どもの視線から1945年から40年後のドイツの社会の実相を写そうとする。白黒であることがドキュメンタリー性をいっそう強調するが、実際は天使がそれを観察しているという空想性が基本ポイントだ。
ああ いつの日か おそるべき洞察の果に立って
肯う天使らに 歓呼と讃頌の歌を 高らかに歌わんものを。
( 中略 )
飲む者がい.つも新鮮な「気晴らし」をつまみに噛っていれぱ
甘い味がするように思われる あの「不死」という苦いビールの
広告が貼ってある最後の板塀の向うには
そのすぐ背後 すぐその向うには真実がある
そこでは子供らが遊び 恋びとたちは寄りそうて――離れたところで
真面目な顔つきをしながら とぼしい草地に坐り そして犬たちは自然のすがたをしている
若者はさらに彼方へ惹かれてゆく たぶん彼はひとりの若い「嘆き」を
愛しているのだろう・・・彼女のあとから牧場へ入ってゆくと 彼女が言うのだ
――遠く あの向うに私たちは住んでいます……
何処に? そして若者は
ついてゆく 彼は女の姿態に 肩や頸すじに 心を動かされている――たぶん
彼女は立派な家柄の娘なのだろう けれども彼はまた腫をかえし 彼女をすてて
ふりかえり 手をふる……どうなるというのだ? 彼女は「嘆き」なのだ
( リルケ「ドウィノの悲歌」 第十の悲歌 富士川英郎 訳 )
ちなみに「ベルリン天使の詩」の続編として「時の翼にのって」が1993年に公開され、これはカラーで、マリオンと幸せな家庭を築いているダミエルの友達、天使カシエルが主人公となった映画である。もちろんベルリンの壁は崩壊し去った後のドイツが描かれている。ベルリンの壁を思考の中心に置きたい場合これら2作の映画はよい参考となるかもしれない。アア、それにヴァイツゼッカーの「ドイツ統一への道」とうい本なども・・・
2013.3.4